文 : 鈴木淳史


Wed.5.Dec.2012
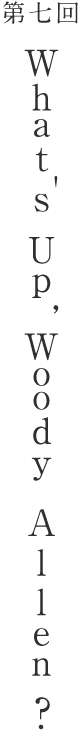
ウディ・アレンのドキュメンタリー映画「映画と恋とウディ・アレン」を鑑賞した。1960年代後半から、ほぼ毎年1本を撮り続けているという。サブカル文系少年を気取っていた僕は、当たり前の如く導かれるかのように90年代の多感な時期に出会った。何かひねくれている、何か不満そう、でも常にロマンチックな恋を求めるウディに、「この人は、僕に似ている」なんていう、ありがちな思い込みで好きになったものだ。
アカデミー賞やカンヌ常連の映画人ながら、権力に傾くことなく、常に斜に構えている。2011年に75歳でメガホンを取った「ミッドナイト・イン・パリ」では、彼史上最高の興行収入をあげるという快挙を成し遂げた。それでも、彼は「映画と恋とウディ・アレン」のラストシーンで、こう呟く。
「こんなにも運が良かったのに、人生の落伍者の気分なのはなぜだろう」
そのひとことに、とんでもなく救われた。誰よりも表現を愛している自信を持ち、誰よりも幸福を願っているのに、浮かれきって間違えたハッピーな雰囲気を醸し出している空間に、34歳になっても全く馴染めない。自分がずっと愛している演者でも、流行となり旬となった事で本質を見ずに”売れている”という事実だけで乗っかり、我が物顔で「我らが!」なんて…、演者を持ち上げている人たちを見ると吐き気をもよおしてしまう。きっと、その人たちは…、去年は違う演者に、来年は違う演者に、同じ台詞を間抜け面で言っているのだろう。何で、心から愛するっていう、そんな簡単な事ができないのだろうと、勝手にずっと怒り悲しみ悩んでいた。
だからこそ、ウディの言葉に、とんでもなく救われた。ウディのような人でさえ孤独と向かい合っているのだから、僕のような単なる裏方が孤独のどん底にいたって何もおかしくない。そして、とことん孤独のどん底から本物の演者を応援し続けようと思わされた。
ドキュメントの中で、ウディは極度のインタビュー嫌いを明かしている。僕は今年、学生時代からずっと憧れていたお笑いコンビの方にインタビューができた。周囲には驚かれ、「もう、インタビューしたい人なんていないでしょ!? もう、あがり(引退)だね!!」なんて冗談交じりに言われるくらい、それは或る意味、快挙であった。燃え尽きてしまうかな…、そんな自分の予想とは反対に、憧れに到達したからこそ、もっともっとインタビュー道を極めたいと燃えられた。
そう、僕は新たな獲物を見つけてしまった。「映画ライターじゃないでしょ?!」、「英語話せないでしょ?!」、「来日しないよ?!」…、やってみないとわからない。憧れの人を本気で想って、本気で愛していたら逢えてしまうのが、この仕事の素晴らしすぎる魅力だ。ウディ・アレンに、必ずインタビューで出逢いたい。
そして、こんな浮かれポンチな汚れちまった世界でも、強い気持ち強い愛で生き抜いてやると…、勝手に意気込んでいる。2013年も良い年になりそうだ。〆っぽい事を記しましたが、年内、後もう1回コラムは残っているんですけどね…。おあとがよろしいようで。
ARCHIVES
- ▷ Mon.22.Sep.2014 「僕とテレキャノとロフト。」
- ▷ Tue.1.Apr.2014 「ABCラジオの時間。」
- ▷ Thu.9.Jan.2014 「たまたま埼玉」
- ▷ Wed.8.Jan.2014 「モテキ2014」
- ▷ Thu.12.Dec.2013 「冬の終わり~その時、ボクのハートは盗まれた~」
- ▷ Tue.3.Dec.2013 「少女A~中で学ぶ~」
- ▷ Mon.2.Dec.2013 「SUZUDAMA2013」
- ▷ Wed.16.Oct.2013 「Suzudama Times完成」
- ▷ Tue.15.Oct.2013 「一生忘れられない歌」
- ▷ Thu.15.Aug.2013 「サマージャム’13」
- ▷ Fri.9.Aug.2013 「デラシネ」
- ▷ Sun.4.Aug.2013 「8月8日は、『パプアニューグリラ祭』です♪」
- ▷ Mon.22.Jul.2013 「ほんまもんのレストラン」
- ▷ Thu.18.Jul.2013 「夏にして彼を想う」
- ▷ Wed.3.Jul.2013 「めひかりくるり」
- ▷ Fri.28.Jun.2013 「ギラギラ輝いていたヒマワリ…」
- ▷ Fri.21.Jun.2013 「オカンとピエールさんとマヤカン」
- ▷ Thu.13.Jun.2013 「50歳で出逢ったロックンロール」
- ▷ Thu.30.May.2013 「5月に捧ぐ」
- ▷ Wed.29.May.2013 「KING BROTHERSは不死鳥」
- ▷ Thu.16.May.2013 「雑誌広告のウワサの真相」
- ▷ Mon.13.May.2013 「日本語”プチ”研修中」
- ▷ Wed.1.May.2013 「レッドスニーカーズ×5月6日×シャングリラ」
- ▷ Fri.26.Apr.2013 「春の我が家の夕食」
- ▷ Fri.19.Apr.2013 「ほめてよ」
- ▷ Fri.12.Apr.2013 「離島に暮らす我が姪っ子」
- ▷ Sat.6.Apr.2013 「bloodthirsty buchers×KING BROTHERS」
- ▷ Fri.29.Mar.2013 「寅!寅!寅!」
- ▷ Thu.21.Mar.2013 「とりまきぐるぴ」
- ▷ Wed.20.Mar.2013 「太陽の塔」
- ▷ Fri.8.Mar.2013 「33」
- ▷ Wed.27.Feb.2013 「裏万博閑話」
- ▷ Mon.25.Feb.2013 「現場後記」
- ▷ Sat.16.Feb.2013 「タラモサラータ」
- ▷ Wed.13.Feb.2013 「ままぼく」
- ▷ Tue.5.Feb.2013 「ドナルド・キーン」
- ▷ Thu.24.Jan.2013 「いじめといじり」
- ▷ Thu.17.Jan.2013 「1月17日」
- ▷ Thu.10.Jan.2013 「古都からの若き刺客たち~2013年~」
- ▷ Thu.27.Dec.2012 「2012 BEST LIVE BAND」
- ▷ Thu.20.Dec.2012 「心のベスト10第一位は、こんな曲だった~2012年~」
- ▷ Wed.12.Dec.2012 「国境とパスポートと私」
- ▷ Wed.28.Nov.2012 「パリへの道中」
- ▷ Thu.22.Nov.2012 「後60分…」
- ▷ Wed.14.Nov.2012 「ハテナをミキサーにかけて」
- ▷ Fri.9.Nov.2012 「耳鼻咽喉科」
- ▷ Wed.31.Oct.2012 「”マヤカン”は遠くにありて思うもの」
- ▷ Wed.24.Oct.2012 「ライナー&ノーツ」
- ▷ Wed.17.Oct.2012 「2作目は機関銃を持って…」
- ▷ Wed.10.Oct.2012 「ラーメン!つけ麺!実母そうめん!」
- ▷ Wed.3.Oct.2012 「イライラをミキサーにかけて」
- ▷ Wed.26.Sep.2012 「そうだ!10月5日金曜日は、梅田クアトロの『SUZUDAMA’12~鈴木魂~ 新座長襲名公演』へ行こう!!」
- ▷ Wed.19.Sep.2012 「ランゲージとカルチャー」
- ▷ Sat.15.Sep.2012 「モテてんじゃねぇよ!モノ珍しがられてんだよ!」