文 : 鈴木淳史


Wed.13.Feb.2013
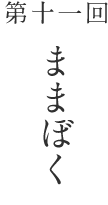
オカンなんていう便利な言葉を使って、母親を紹介して、一緒にリレーコラム連載なんて事までやらせてもらっている。ただ、1980年代の阪神地域には、そんな言葉は存在しなかった。だから僕は、こう呼んでいた『ママ』と…。この言葉に、その後とんでもなく苦しめられるとは当時思いもよらなかったが。
大学時代、世間的に学生運動が盛り上がっていたらしいが、ママは既に高校時代に経験済みだったため、学生食堂でひとりアコギ片手にボブ・ディランを歌っていたという。そんなノンポリヒッピーなカレッジライフの後は、万博のコンパニオンに。最初に決まったある日本の企業館とは研修時に喧嘩別れ。が、親に示しがつかないと、ある外国館の面接に、何故か着物姿で登場したという。そのため、ほとんどタイプライター試験がおぼつかなかったらしいが、持ち前の愛嬌で乗り切ったらしい。てな感じで気が付けば外国暮らし、そして帰国しバブルが来る前に勝手に弾けてしまう我が父と結婚…、で、僕が生まれるわけだ。僕が幼稚園年長の時に見事別居し、実家である阪神地域へと戻ってくる…と駆け足ダイジェストでお送りしたが、ここからがママと僕との深くも濃いい話になる。
164センチで50キロを切る体型からは見掛けも寄らず、ママは常にパワフルだった。僕が小学生低学年の時、細腕にも関わらず片方に同級生をひとりずつぶら下げて筋肉モリモリポーズを取ったりしていた。完全に男親のする技だ…。街頭テレビで力道山を観ていた世代でプロレスが好きだったため、こういう力技が大好きだった。同じDNAが流れていたのかプロレスにはまっていく僕に、ある日ママはこう言った。「ママね、昔、女子プロレスラーだったの。でも体重がないから、ベルトは取れなかったんだけどね」。アホな僕が、それを信じないわけがない。疑う余地なく、翌日僕は学校中で先生、生徒、教育実習生誰かれ問わず話しまくっていた。その後、どうやらママは、とんだ恥をかいたらしいが、そんなのは知った事でない。本人の口が災いの元である。まぁ、裏付けるわけでないが、本当に当時のママは女子プロ並みに強かった。プロレスごっこをしては、僕をスリーパーホールドで締め落とし泡を吹かせた事も…。電話帳ほどの分厚さがある少年漫画雑誌ばっかりを読んで勉強をしない僕から、雑誌を奪い取り破り裂いた事もあった。りんごを握り潰すパフォーマンスをした外国人レスラーを思い出し、僕は縮み上がったものだ。女手ひとつで育てていた事もあり、とにかく厳しくて怖かった。ある夜、怒られた僕が泣き喚くと、近所迷惑を考えたママは車で近くの山へと連れて行った。不良でお馴染みの高校が近くにあり、その上、野良犬が吠える山…。震え上がって動けない僕を引きずり下ろし、置いて帰ろうとした。容赦なさ過ぎである…。
そんな僕も何とか中学3年生になった1992年、「ずっとあなたが好きだった」というドラマが大流行した。いわゆる、“冬彦さんブーム”というやつである。要はマザコン具合をデフォルメした冬彦さんという登場人物の奇怪さが人気を博したわけで、僕もいちドラマとしては非常に引き込まれた作品であった。が、多感な中学生たちが、その話題を放っておくわけがない。僕とママの関係を、冬彦さんとそのお母さんの極度なマザコン状態に置き換え、イジリ始めてきたのだ。それ以前からにも、ママとの関係をイジリ出してきた彼らにとって、冬彦さんは勝手の良い題材だったのだろう。そのイジってきたメンバーの中心人物たちが小学校からの同級生で、家族ぐるみの付き合いをしていた奴らだったというのもおもしろい。つまり彼らからすると、ステレオタイプに大人びた独立した中学生を演じているのに、母親と仲の良いままを保っている友達がいたら厄介だったというのがあったのだろう。でも申し訳ないが、こちらは自分の事しか興味ないし、「あいつ悪ぶってるけど、実はお母さんの事を『ママ!』って呼んでるぜ!!」とか暴露するわけがない。我の保身の為に友達を貶めるというのは、ある意味人間味がある。
今となっては落ち着き払って語っているが、当時の僕は初めてぶち当たる“ママ問題”にとんでもなく苦しめられた。というか、非常に迷惑だったというのが本音である。誰にも迷惑かけていないのだから、人ん家の状況は放っといてほしいという感じだった。近くのスーパーにママと出掛けても、同級生たちがいたら慌てて隠れたりしたものだ。当の本人であるママには面と向かって何も言えず、しおらしくはにかむ彼らも、いざ本人がいなくなったら「派手だ!」、「煙草吸っている!」、「学校にいた!」と好き放題言ってネタにしていた。最後の「学校にいた!」に関しては、父兄参観やPTA会議だからいて当たり前なのだが、何か言いたいのだろう。もちろん、ママという呼び名も言葉狩りにあい、彼らの前では言えなかった。ママという言葉ほど、思春期の子供たちから馬鹿にされる和製英語はないだろう。家から少し離れた私立の高校に行ってからは、中学校ほど言われなくなったが、それでも言いたがる奴はまだ若干残っていた。
流石に大学になると我の保身の為に身を貶める感覚も無くなるのか、同級生たちは愉快な豪快なお母さんという捉え方で、おもしろがってくれるようになった。社会に出てからもそうで、ファンキーなママというイメージを持ってくれ、「ウチの母親は、こんなんじゃない! 素敵だ!」なんて言って、ママと知り合いたちが一緒に飲んだりまでしている。あれだけ蔑まされたママという言葉も、こちらが使わずとも勝手に「ママ~!」などとみんな呼ぶ始末。気が付けば、僕よりも人気のある存在に。不思議なもんだ。ママ自体は中高時代の事を未だに覚えているのか、ママという言葉を避けて、いちいち「淳史に『お母さん、それは駄目やって!』と言われたの!」と気を遣って言葉変換をしてくれたりしている。
数年前に“オカン”をテーマにした本や映画、ドラマがあった事もあり、今やオカンという言葉を使わない都会の人間までもが「オカンがさ~」なんてほざいて、母親を大切にする自分を演出し、女子の気を惹こうとする。そんな奴に限って中高時代、母親の存在を封印しようとしていただろう。僕自身、中高時代にママという存在を馬鹿にしていた奴らには「僕は何も間違えてなかったでしょ」と言いたい。一貫してママという存在を僕が一度も封印しなかったのは、ママがおもしろかったからだ。
最近では僕の知り合いたちから、ママの言葉を知ったりする事も多くなった。ちょうど昨年の震災があった時、知り合いに阪神淡路大震災の話を振り返りながら「家が全壊したんだけどね、一番最初に淳史の制服を瓦礫の中から引っ張りだしたの。何せ、学校に行かしてやらないといけないと思って」。初めて聞いた話だけに、ちょっと言葉を失ったものだ。そんなママは去年の暑すぎる夏も毎日僕のTシャツに丁寧にアイロンをかけながら、「あんたにとってのTシャツは、みんなにとってのスーツなんだからね」と言っていた。わかりやすいサラリーマンにならず、フリーランスで仕事をする僕に敬意を払ってくれている。ありがたい話だ。
一風変わったママだが、常に本気で僕を想い、育てあげる事に命を懸けてくれた。今も尚、同居して脛を齧っている訳だから、ママの子育ては現在進行形なのかも知れない。感謝せざるをえない。ママに比べて、昔と変わらずそのままの僕である…、そんな事を35歳になった2月ふと想ってみたりした。
おあとがよろしいようで。
ARCHIVES
- ▷ Mon.22.Sep.2014 「僕とテレキャノとロフト。」
- ▷ Tue.1.Apr.2014 「ABCラジオの時間。」
- ▷ Thu.9.Jan.2014 「たまたま埼玉」
- ▷ Wed.8.Jan.2014 「モテキ2014」
- ▷ Thu.12.Dec.2013 「冬の終わり~その時、ボクのハートは盗まれた~」
- ▷ Tue.3.Dec.2013 「少女A~中で学ぶ~」
- ▷ Mon.2.Dec.2013 「SUZUDAMA2013」
- ▷ Wed.16.Oct.2013 「Suzudama Times完成」
- ▷ Tue.15.Oct.2013 「一生忘れられない歌」
- ▷ Thu.15.Aug.2013 「サマージャム’13」
- ▷ Fri.9.Aug.2013 「デラシネ」
- ▷ Sun.4.Aug.2013 「8月8日は、『パプアニューグリラ祭』です♪」
- ▷ Mon.22.Jul.2013 「ほんまもんのレストラン」
- ▷ Thu.18.Jul.2013 「夏にして彼を想う」
- ▷ Wed.3.Jul.2013 「めひかりくるり」
- ▷ Fri.28.Jun.2013 「ギラギラ輝いていたヒマワリ…」
- ▷ Fri.21.Jun.2013 「オカンとピエールさんとマヤカン」
- ▷ Thu.13.Jun.2013 「50歳で出逢ったロックンロール」
- ▷ Thu.30.May.2013 「5月に捧ぐ」
- ▷ Wed.29.May.2013 「KING BROTHERSは不死鳥」
- ▷ Thu.16.May.2013 「雑誌広告のウワサの真相」
- ▷ Mon.13.May.2013 「日本語”プチ”研修中」
- ▷ Wed.1.May.2013 「レッドスニーカーズ×5月6日×シャングリラ」
- ▷ Fri.26.Apr.2013 「春の我が家の夕食」
- ▷ Fri.19.Apr.2013 「ほめてよ」
- ▷ Fri.12.Apr.2013 「離島に暮らす我が姪っ子」
- ▷ Sat.6.Apr.2013 「bloodthirsty buchers×KING BROTHERS」
- ▷ Fri.29.Mar.2013 「寅!寅!寅!」
- ▷ Thu.21.Mar.2013 「とりまきぐるぴ」
- ▷ Wed.20.Mar.2013 「太陽の塔」
- ▷ Fri.8.Mar.2013 「33」
- ▷ Wed.27.Feb.2013 「裏万博閑話」
- ▷ Mon.25.Feb.2013 「現場後記」
- ▷ Sat.16.Feb.2013 「タラモサラータ」
- ▷ Tue.5.Feb.2013 「ドナルド・キーン」
- ▷ Thu.24.Jan.2013 「いじめといじり」
- ▷ Thu.17.Jan.2013 「1月17日」
- ▷ Thu.10.Jan.2013 「古都からの若き刺客たち~2013年~」
- ▷ Thu.27.Dec.2012 「2012 BEST LIVE BAND」
- ▷ Thu.20.Dec.2012 「心のベスト10第一位は、こんな曲だった~2012年~」
- ▷ Wed.12.Dec.2012 「国境とパスポートと私」
- ▷ Wed.5.Dec.2012 「What’s Up, Woody Allen?」
- ▷ Wed.28.Nov.2012 「パリへの道中」
- ▷ Thu.22.Nov.2012 「後60分…」
- ▷ Wed.14.Nov.2012 「ハテナをミキサーにかけて」
- ▷ Fri.9.Nov.2012 「耳鼻咽喉科」
- ▷ Wed.31.Oct.2012 「”マヤカン”は遠くにありて思うもの」
- ▷ Wed.24.Oct.2012 「ライナー&ノーツ」
- ▷ Wed.17.Oct.2012 「2作目は機関銃を持って…」
- ▷ Wed.10.Oct.2012 「ラーメン!つけ麺!実母そうめん!」
- ▷ Wed.3.Oct.2012 「イライラをミキサーにかけて」
- ▷ Wed.26.Sep.2012 「そうだ!10月5日金曜日は、梅田クアトロの『SUZUDAMA’12~鈴木魂~ 新座長襲名公演』へ行こう!!」
- ▷ Wed.19.Sep.2012 「ランゲージとカルチャー」
- ▷ Sat.15.Sep.2012 「モテてんじゃねぇよ!モノ珍しがられてんだよ!」